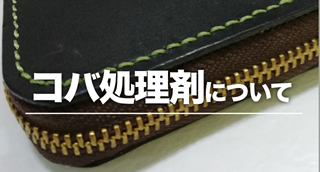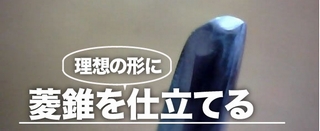菱錐で穴をあける方法

ここでは静かにレザークラフトを楽しむ時の菱錐(キリ)で穴をあける時の使い方を考えていきます。
錐を使う心構え

錐自体はシンプルなつくりなので使い手の考えや技術などにより差がでやすいです。
力を加えて1つ穴をあけるだけならとても簡単ですが、綺麗な縫い穴をたくさんあけて 綺麗な縫い目を作る為にはコツがいります。
安い錐がだめで、高い錐は綺麗に縫い目を作れるというモノではありません。大事なポイントを正しく知り それを実行し守る技術が必要です。
■ 錐を使う時に忘れてはいけない大事なポイント
- 穴を縁から一定ラインに揃える
- 穴と穴の間隔を一定にする
- 穴の角度を一定にする
- 穴の大きさを一定にする
- まっすぐ穴をあける
- 重ね合わせた革は ずれないように
- カーブやコーナーの穴の角度

言うだけなら簡単なのですが。。。練習あるのみですね♪
大事なポイントを守れば既グッと仕上がりがよく既製品のような感じになりますよ♪
※無料の菱錐練習用シートもあります。
大事なポイントの解説

大事なポイントはお互いに関係し、影響しあっているので どのポイントも大切にするのが基本です。
■ 穴を縁から一定ラインに揃える
菱目打ちなどでも使われている技法ですが、ディバイダーを使って縁から決めた幅に縫い穴ラインを引く方法がお気に入りです。
もちろんステッチンググルーバーも 革に掘ったラインの太さと錐の太さが同じ位なら均一なラインで穴あけしやすいと思います。
裏技的に菱目打ち(2つ目)で縁から一定ラインをひく事も可能です。
■ 穴と穴の間隔を一定にする
穴の間隔がバラバラなほど不細工なモノはありません。穴の間隔を均一にするには 穴あけ位置の目印を均一に記しておく必要があります。下記のいづれかの方法で縫い穴を均等にあけるように目印をつけましょう。
目印のつけ方
- 菱目打ちで軽く打つ方法
1番おススメな方法で あのエルメスの職人さんも使っているやり方です。
穴をあける場所に軽く目打ちで目印を作り、その後 目印に菱錐で穴をあけていきます。
※目印は軽く叩くとつきます。貫通させず向きがわかる程度で十分です。
2度手間のような気がしますが、穴がきれいにあく事、静かに作業ができる事がメリットです。
個人的にはヨーロッパ目打ちの方が菱錐の角度をあわせやすく目印もつきやすいのでお気に入りです。目印用と割り切ったならヤフオクで安いヨーロッパ目打ちでも充分だとおもいます。また刃数の多い目打ちは直線がでやすく、時間も短縮できるので◎
【方法】
- ディバイダー等で縁からの縫い穴ラインを引く
- 菱目打ちをラインに合わせて軽く木槌等で叩いていく
- 革にできた目打ちの跡を確認
- 目印と錐の刃先を合わせながら穴をあけていく
※ほかの注意事項も守りながら穴をあけましょう。
※ヨーロッパ目打ちを使うと菱錐の角度あわせしやすいので◎
- 型紙に穴あけ位置を記しておく方法
作品の型紙に錐用の穴位置を設けて、そこを目印に穴あけしていく方法です。
穴あけ用の治具とよんでもいいかも知れません。1度作成すれば再利用する時に楽チンです。 無料の型紙で錐用の穴あけ位置を明記した型紙は少ないのが現状で自分で作成するのが基本になると思います。
※少しですが当サイトこちらでも提供しています。充実させていきますね♪
- ディバイダーでつける方法
1つずつしか穴をあけられませんが 菱目打ちを持っていない時、小物やカーブやコーナー部分などでは役立ちます。
【方法】
穴と穴の間隔を決めてディバイダーにあわせる。開始位置を決め穴をあけ、あけた穴に片方の足をかけ 順番に目印をつけていく。
- ステッチルレットでつける方法
安もの?私の使い方が間違えている?ラインと穴のずれが生じてうまくいかないので使用していません。 - 菱錐用の治具
ステッチメーカー ENGAWA TOOLのような治具です。
一定間隔で穴があいている治具で直線も曲線にも対応していました。作品や場所に合わせて穴あけできるので便利そうです♪欲しい♪
レーザー加工機で自作できるかな?!
革の種類によっては目印をつけても見にくい場合が付けにくい場合はこちらを参照
■ 穴の角度を一定にする。
綺麗な縫い目に直結する大事なポイントです。
通常は表から見て 鋭角の部分が左斜めが上で右斜めが下の30度から60度くらいの範囲の角度がつくと思います。
がんばって手首を固めて一定の角度で穴あけしていきましょう。
目印が菱目やヨーロッパ目ならその角度に合わせて穴をあけていきましょう。
穴の目印が丸の場合は自分で角度を作って その角度を維持しながら全体の穴あけ作業をしていきます。
持ち手の部分にマジックで角度の目印ラインをいれる方もいますよ♪
こちらでは30度,45度,60度の角度で穴あけ練習できるシートを提供しています。
■ 穴の深さを一定にする
共進エル社の菱錐など太さが一定の錐なら気にしないでいい部分です。
先端が細く、根元にいくほど太くなる錐の場合は 錐の差し込み深さを一定にしないと穴の広がりにバラつきが生じ、縫い目自体もバラバラになってしまいます。
錐の方に目印をつけるか、貫通しやすいコルク板と貫通しづらいゴム板の厚さを調整し錐の差し込み量が一定になるような環境を作りしょう。
持ち方
一定の角度で錐を持ち 一定のリズムで上下させやすい持ち方がおすすめ。
そしてその状態で穴あけ作業をたくさんこなしても疲れにくい持ち方が◎
力を入れないと穴があけられないなら一度刃先を研いだ方がいいと思います。
また一定の角度を保ちにくい場合は 菱錐の持ち手部分に目印をつけると刃先を見ないでも角度の確認ができるので便利です。
下の台
平置きして革に穴をあける時は、コルク板が王道でゴム板は硬くて使えません。
錐の刃先は細いので守ってあげましょう♪
私は100均のコルク板をつかったりしますが 深くさしてコルク板を貫通させて机を傷つけないように気を付けています♪
ただ柔らかすぎる素材は穴あけ時に革もたわんで穴あけ精度に影響していまうので綺麗な縫い目を作るにはよくありませんよ♪
もちろんレーシングポニーに挟んで穴あけする場合は下の台はいりません。
穴のあけ方
穴をあける前に正しい持ち方の確認、下の台を準備しましょう。
そして最初の1刺し目をどこにするか決めて穴をあけていきます。
穴あけ目印からのずれ、菱錐の角度、菱錐が垂直になっているか?を常に注意しましょう。
【穴をあける時のコツ(平置き時)】
穴あけ対象の真正面に位置し、体(頭・胴)を動かさずに しっかりもった錐を上下と前後移動だけさせて穴をあけていきます。ロボットのように一定範囲内を上下させていくのが理想です。
しかも縫い穴の角度を一定にしたいので 当然錐の方も一定の角度で動かさない事も重要。そしてコーナーやカーブ部分に達したら縫い穴の角度がうまくつながるように革の方を少しずつ動かしていきましょう。
必要最小限の動きでぶれないよう、疲れすぎないような 自分だけの持ち方や姿勢を見つけましょう。
錐の研ぎ方
日々のちょっとしたお手入れは研磨剤で軽く磨く
いい状態だと力を入れなくてもヌッとかスッと切れ込んでいく感じになります。
お手入れの頻度は錐の材質や感覚の違いもあり一言では難しいですが、キレが悪い、抜けが悪いと感じた時だと思います。よくサクッという感じの切れ込みになったら研ぎが必要とか言われます。
コルク板に置いた状態ではわかりずらいので レーシングポニーのように浮かした状態とかの方が切れ味は分かりやすいと思います。
研いだ後は刃先が傷つかないようにカバーして保管しましょう。もちろん革で作ってもいいですし、コルクでおしゃれなカバーを作ってもいいと思います。
【菱錐に関連するページ紹介】

- 錐の特徴…メリット・デメリットなど
- 菱錐で穴をあける…きれいな縫い目の為のポイント
- 理想の菱錐に仕立てる…好きな形に
- 菱錐の一覧…イロイロあります
- 菱錐練習シート(直線)…PDFで無料提供
- 菱錐練習シート(コーナー部)…PDFで無料提供
- 静音マシンから菱錐派へ…菱錐派になるまでの思い出